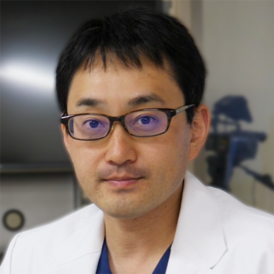肺がんの検査と薬物治療
佐々木 高明 先生
旭川医科大学病院
肺がんと疑われたときの検査
会社の健康診断などで肺がんの疑いがあるといわれた患者さんに対して、紹介されてきたその日のうちにレントゲン検査とCT検査※1で画像を撮り、肺がんであるか確認します。
やはり肺がんであると疑われた場合、診断を確定するために気管支鏡検査(肺のカメラ)※2を行います。

※1:CT検査は、からだの断面画像や立体画像から、がんの大きさ、がんの広がり、がんの性質などがわかる検査です。
※2:気管支鏡検査は、肺の内視鏡と呼ばれ口や鼻からカメラのついた細い管を入れて、肺のなかを検査します。ここで、がんと疑われる場所の組織や細胞を採取してきます。
肺がん治療のための検査
レントゲン検査、CT検査、気管支鏡検査などで肺がんと診断された場合、次にがんの広がりがどのようになっているか検査します。
肺がんの広がりとは、どこまで転移しているか診断するための大切な検査で、PET検査※3やMRI検査※4を使います。
また検査結果から外科的手術が検討出来そうな場合は、患者さんの全身状態を知るために肺活量や心電図なども検査をします。
肺がんには、大きくわけて小細胞肺がんと非小細胞肺がんがあります。この診断には、気管支鏡検査などで採取してきた細胞を、顕微鏡で観察し細胞の形などから確定します。
肺がんの分類と特徴
1. 非小細胞肺がん(約85%)
Ø 腺がん(約55%) 女性の非喫煙者に多く、男女比は約2:1
Ø 扁平上皮がん(約25%) 男性の喫煙者に多い
Ø 大細胞がん(少ない) 男性に多く、進行がはやい
2. 小細胞肺がん(約15%) 男性の喫煙者に多く、進行がはやく転移しやすい
※3:肺がんのPET検査は、全身のどこかに転移をしていないか診断する検査です。
※4:肺がんのMRI検査は、がんが脳に転移していないか確認する検査で、CTと違い放射線を使わないため検査を繰り返すことができます。
小細胞がんの治療法
肺がんは、小細胞肺がんと非小細胞肺がんに大きくわかれます。

非小細胞肺がんは肺がんの大半を占めることからたくさんの情報をもっていますが、小細胞肺がんになると少し特殊性があります。
小細胞肺がんの特徴は、発見された時点でかなり進行している場合が多いといわれています。そのために外科的な手術ですぐに切除することが出来にくく、薬物療法と放射線治療になります。
選択肢が増える肺がんの薬物療法
現在、肺がんを治療する選択肢が広がっています。以前と違うのは、やはり分子標的薬が加わったことです。
分子標的薬は、がんのなかの遺伝子異常を狙って攻撃できる薬剤のため、肺がんの薬物治療において1番大きな進歩になっていると思います。
いまの肺がん治療における分子標的薬のターゲットになる遺伝子異常は、EGFR、ALK、ROS1、BRAFの4つがあります。それぞれの遺伝子異常に効果を示す分子標的薬が決まっています。

遺伝子異常と分子標的薬
Ø EGFR遺伝子変異
ゲフィチニブ(イレッサ錠)、エルロチニブ(タルセバ錠)、アファニチブ(ジオトリフ錠)
Ø ALK融合遺伝子変異
クリゾチニム(ザーコリカプセル)、アレクチニブ(アレセンサカプセル)、セリチニブ(ジカディアカプセル)
Ø ROS1融合遺伝子変異
クリゾチニム(ザーコリカプセル)
Ø BRAF遺伝子変異
ダブラフェニブ(タフィンラーカプセル)、トラメチニブ(メキニスト錠)
腺がんの遺伝子変異と分子標的薬の特徴
非小細胞肺がんは、腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんにわかれます。このなかで遺伝子異常が発見されるのは、大半が腺がんになります。

腺がんの遺伝子変異の割合は、おそらく半分くらいがEGFR遺伝子変異になります。その他に、ALK遺伝子融合が大体5%程度、ROS1遺伝子融合が1〜2%、BRAF遺伝子変異が1%以下といわれています。
一般的に使用されている分子標的薬は内服薬であり、通常に使われている抗がん剤の点滴に比べると、外来治療もできる簡便な薬物治療法になります。また分子標的薬は、副作用が比較的少なく、良く効く、長く効くという3点が特徴となっています。
現在の分子標的薬は、他の薬物療法と併用せずに単剤で使用されます。ただし、分子標的薬単剤で効果がなくなってきたときは、次の薬物治療として通常の化学療法が大事な役割を果たします。
佐々木高明先生からのメッセージ
肺がん患者さんが納得した治療を受けていただくために、主治医の先生と現在の治療が良いのかよく話し合ってください。
いまのところ、何か遺伝子異常が発見されても前述した4つの遺伝子変異以外の分子標的薬がないからです。しかし、日本の肺がん治療は日々変化しており、昨年の治療が古くなる時代です。つまり新しい薬剤が登場する時代となっているので、主治医の先生との話し合いが大切なのです。