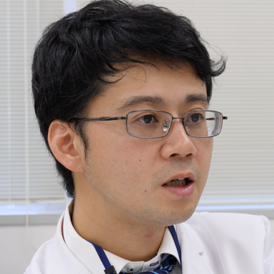非小細胞性肺がんの分子標的治療、専門病院で受けるステージⅣの治療とは
田中 寿志 先生
弘前大学医学部付属病院
分子標的治療!この方針が決まるまでの流れ
分子標的治療ができるかできないかの方針は、まず患者さんの全身状態がわかる患者背景から判断し、次に治療に大きく関係する腫瘍由来のデータによって決定します。
腫瘍由来のデータとは非小細胞肺がん患者さんが持っている特定の遺伝子変異のことで、この遺伝子を持っている場合、分子標的薬を選択する治療方針になります。
さらに、いま免疫治療が非小細胞性肺がん患者さんに初回治療として使えるようになっていることから、腫瘍免疫のタンパクの状態によっては免疫治療を選択する治療方針があるのです。
ステージⅣの全身状態を判断する評価、パフォーマンス・ステータス
ステージⅣの非小細胞性肺がん患者さんの治療方針を決めるとき、まずは全身状態を調べるためにパフォーマンス・ステータス※1の評価を使います。

まずこの評価を使い、全身状態が良いか、日常生活に問題がないか、寝たきりに近い状態まで体力が落ちていないかなどに治療方針を分けることになります。
つまりパフォーマンス・ステータスは、抗がん剤には基本的に副作用が発生することから、患者さんの身体がこれについていけるか判断するための因子になるのです。
この結果より、患者さんが抗がん剤の治療についていけそうな体力をもっていると判断できた場合、分子標的治療を受けるための腫瘍因子を検査するステップへ進みます。
※1 パフォーマンス・ステータス:患者さんが身のまわりのことをどこまでできるか判断するための尺度です。0〜4までの5段階評価になっており、数字が小さいほど全身状態が良いことになります。
分子標的治療が選択できる、保険適応の腫瘍因子とは
現在、健康保険を使って検査ができる腫瘍因子は、ALK※2・EGFR※3・ROS1※4になります。

まずは、これらの遺伝子変異のある非小細胞性肺がん患者かどうかを検査によって判断し、遺伝子変異がある場合、それぞれにあった分子標的薬を選択します。
しかしこの検査の結果から、遺伝子変異がない患者さんもいます。
このようなときは、患者さんから採取した生検検体からPD-L1というタンパクを測り、これが50%以上有る場合、免疫治療を初回治療として選択するか判断します。
※2 ALK:ALKの融合遺伝子があると、ここからできたたんぱく質によってがん細胞を限りなく増え続けます。
※3 EGFR:EGFRに変異があるとがんを増殖させるスイッチがオン状態となり、がん細胞が限りなく増え続けます。
※4 ROS1:ROS1の融合遺伝子があると、ALK融合遺伝子と同じような作用でがん細胞が増え続けます。
※5 PD-L1:PD-L1とはがん細胞の表面にある分子で、自己免疫であるT細胞の攻撃をストップさせる働きをもったタンパク。
通常の抗がん剤と分子標的薬の違い、副作用ではどうか
分子標的薬は、通常の殺細胞性※5の抗がん剤と比べると脱毛や血液毒性などの副作用が起こりづらいと考えられています。

その代わり特徴的な副作用として、皮膚毒性※6がほとんどの分子標的薬で発生します。
さらに分子標的薬によっては、強い下痢を起こすこともあります。
また特に注意が必要な副作用として、薬剤性の肺炎※7が殺細胞性の抗がん剤より発生頻度が高いといわれています。
※5殺細胞性抗がん剤:血流が多く細胞分裂が激しいがん細胞を死滅させるため、正常な細胞まで攻撃する抗がん剤。
※6皮膚毒性:EGFRは皮膚の上皮成長因子、ALKは血管の内皮成長因子に作用することから副作用が発生する。
※7薬剤性の肺炎:発症する理由は不明であるが、上皮成長因子や血管内皮成長に作用するための免疫作用が考えられています。
効果が期待できる分子標的薬、専門の病院で幅広い治療を受けるためには
分子標的薬は、非小細胞性肺がんに対して奏効する確率が高いといわれています。
一般的には、70〜80%程度の奏効率※8が見込まれていることから、効きやすい薬剤と考えられています。
しかし半永久的に効果を続けている患者さんは少なく、10〜13ヶ月くらいで薬剤性の耐性ができるといわれているのです。
現在、EGFR遺伝子変異がある患者さんに対してオシメルチニブという薬剤、第3世代のEGFRチロシキキナーゼ阻害剤も使えるようになってきています。

また新しい薬剤が初回治療から使用できるようにもなってきています。
つまり、非小細胞性肺がんに対する分子標的薬は市販されているものや治験中のものがあります。
だから、いま治療を受けている主治医の先生にがん治療について相談し、現在の患者さんの状況によって試すことのできる治験(開発のための臨床試験:フェーズⅡ)があるか、専門の病院でしか治療が受けられない発売されている分子標的薬などを使うことができるように、治療のツールを最大限に活かせることに,唯一の方法を常に情報提供を出してくれる病院を考えてみましょう。
※8 奏効率:奏効率とは、あるがん治療法を患者に用いた際、その治療を実施した後にがん細胞が縮小もしくは消滅した患者の割合を示したもの。