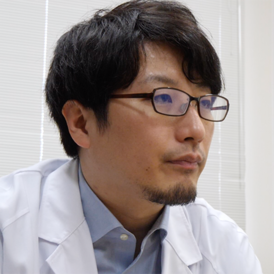非小細胞肺がんの治療法:免疫チェックポイント阻害剤の適応は?ステージで治療法は?
非小細胞肺がんの治療法:ステージやバイオマーカーで選択肢は変わる
非小細胞肺がんの治療は、ステージや各種のバイオマーカーによって、選択肢が大きく変わります。
ステージⅠ・Ⅱ期の比較的早期がんの場合には、第一の選択肢として手術を考えるケースが多いです。
この中でも、高齢者や合併症などの影響で手術が困難であるケースや、Ⅲ期へ進行していく過程で根治的な切除が難しいと考えられる患者さんについては、放射線治療や、放射線治療と抗がん剤を組み合わせた治療を検討します。
さらにステージの進んだⅣ期のケースでは、手術や根治的な放射線治療が適用されません。
したがって薬物療法を用いて治療することになります。
薬物療法の中には、一般的な細胞障害性抗がん剤の他、分子標的薬、免疫療法の3つが含まれており、これらが薬物療法の大きな柱となります。
特に、分子標的薬が適用となるような遺伝子異常を持つ肺がんの患者さんに対しては、分子標的薬を選択することが戦略の1つになります。
また、分子標的薬が適用とならないケースでは、「PD-L1」と呼ばれる免疫療法が効きやすいか・効きにくいかを判断する数値を指標として、効きやすい体質の人には「ペンブロリズマブ」と呼ばれる薬剤を単一で投与します。
この数値が低い人に対しては、細胞障害性抗がん剤と免疫療法を組み合わせた治療を行うことが多いです。
つまり非小細胞肺がんは、各遺伝子異常など細かい指標までを検査しなければ、治療方針が細部まで決まらない疾患であり、その選択肢は患者さんそれぞれによって様々です。
免疫チェックポイント阻害剤の適用は?
非小細胞肺がんに対する免疫チェックポイント阻害剤は、ステージがⅣ期のケースに対して使用してきました。
現在は、Ⅲ期における放射線化学療法の維持療法の1つとしても利用されています。
免疫チェックポイント阻害剤を単一で投与した場合、効果が現れるまでにかかる時間は、従来の細胞障害性抗がん剤と変わらないと言われています。
実臨床の場で実際に患者さんの経過を診ている医師たちの感覚としても、期間に大きな差は無いようです。
ただ、ごく稀ではありますが、「シュード・プログレッション(偽増悪)」と呼ばれる現象が起こることがあります。
これは、免疫チェックポイント阻害剤の治療を開始して1ヶ月後くらいの間に認められるもので、治療をしているにも関わらず腫瘍が大きくなるという現象です。
投与を続けていくことで次第に小さくなることが多いため「偽」増悪と呼ばれるのですが、本当に増悪している可能性も捨てきれないのが難しい点です。
この辺りの作用についても鑑みながら、画像所見などと合わせて、治療の効果を慎重に判断する必要があります。
免疫チェックポイント阻害剤の一次治療:PD-L1の発現率が重要指標に
免疫チェックポイント阻害剤の単一投与では、PD-L1と呼ばれるタンパク質を持っているかどうかが指標となります。
PD-L1を半数以上の細胞で発現している患者さんに対しては、ペンブロリズマブと呼ばれる薬剤を標準治療として使用します。
これは従来の細胞障害性抗がん剤よりも有効性が高いという理由です。
また、PD-L1が50%以上発現していなくても、1%以上の細胞で発現していればペンブロリズマブを保険適用で使用できますが、和歌山県立医科大学では49%以下の発現率の患者さんに対しては細胞障害性抗がん剤を優先して投与しています。
PD-L1発現率50%以上の患者さんに対するペンブロリズマブ単剤治療は、奏効率が4割程度である、という報告がされています。
腫瘍が小さくなる、という点に関しては効果が期待できる治療法です。