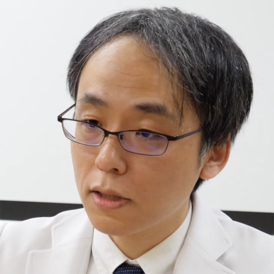大腸がんに対する放射線治療、その適応と効果
坂中 克行 先生
京都大学医学部附属病院
放射線の治療計画
放射線治療においては、がんに対してはしっかり放射線を照射し、周囲の正常な組織には、できるだけ照射せずに治療を行うことが大切です。
腫瘍のある部分のみを狙い打つことで、副作用の少ない治療計画を立てることが肝要です。
放射線のみで治療が完結することは少なく、たいていの場合は、抗がん剤などを併用することで、治癒率の向上に努めています。
術前放射線療法単独の場合と、抗がん薬を併用した術前化学放射線療法の場合における局所再発率を比較した結果によると、術前化学放射線療法の方が、局所再発率を低く抑えられることが分かっています。

がん治療においては、抗がん剤や放射線治療の計画をしっかり立て、なおかつそれらによる副作用のケアを行うことが大切です。
術前の放射線治療で腫瘍サイズを小さくする
たとえば直腸に腫瘍があり、手術を行う場合、直腸は肛門の出口に近い臓器のため、同時に肛門も切除しなくてはならないことがあります。
すなわち、人工肛門になってしまうリスクがあるのです。
肛門を残したいと患者さんがご希望された場合や、あるいは、手術だけで取り切れないと予想されるほど腫瘍が大きい場合、放射線治療を検討します。

京都大学においては、外科や内科の医師と放射線科医とが連携を取り、術前化学療法と放射線治療を行い、腫瘍を小さくすることで、人工肛門を避ける手術や、大きな腫瘍でも手術でしっかり取りきれるような治療を提案しています。
補助療法としての放射線治療を行う時期
補助療法としての放射線治療を行う時期
1. 術前療法
2. 術後療法
の二つがあります。
術前療法は、手術中に散らばる恐れのあるがん細胞を、予め死滅させておくことや、がんを可能な限り小さくし、
手術で腫瘍を切除しやすくすることを目指す目的で行います。
術後療法は、手術で切除しきれずに残ったがん細胞を死滅させ、再発の可能性を下げるために行います。
術前療法を行う場合、画像では腫瘍範囲が広く見えていても、実際手術をしてみると、それほど広がっていなかったという症例が一定数あります。
そういう症例は、本来は、放射線治療や抗がん剤治療が必要ではなかったケースです。
術前に化学療法や放射線治療を行うことは、このように、無駄な治療を受けることになるかもしれないというデメリットもあります。
一方、術後に抗がん剤や放射線による治療を行う場合、手術後の病理検査で、腫瘍があることを確認して治療を行います。
これによって、無駄な治療は避けられますが、手術後に行う治療なので、治療を行ったからといって、人工肛門を避けられるわけではありません。
術前に行う場合と比べて、治療による副作用が増加するとも言われています。
放射線治療を行うのであれば、術前に行った方がよいと考えます。
放射線治療の適応と進歩
その他の放射線治療の適応としては、
1. 手術後、骨盤内リンパ節に再発し、痛みを伴う場合
2. 骨転移を来たし、痛みを伴う場合
3. 脳や肺や肝臓などに転移を来たした場合(転移の個数や大きさによる)
が挙げられます。
放射線治療を行うことで、約7~8割の方において、痛みなどの症状が和らぐと言われています。
近年、転移病変に対する放射線治療の技術は進歩しています。
定位手術的照射(ガンマナイフ)と呼ばれる方法では、一つ一つの病変に対し、そこだけをピンポイントに狙い打つことができます。

以前と比較し、脳の広範囲に当てるのではなく、病変のある部位のみを狙って照射することが可能になりました。
治療における患者さんの負担が少なくなり、病変部もしっかりコントロールできるようになりました。